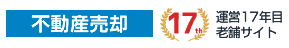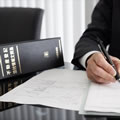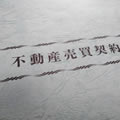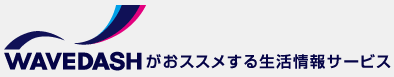あなたの不動産を無料で査定
不動産売却で配偶者控除・社会保険の扶養から外れる?税負担への影響と対策
不動産を売却して配偶者控除・社会保険の扶養から外れるケース、譲渡所得税の仕組みや税金対策

不動産を売却すると、「配偶者控除が適用されなくなる」「社会保険の扶養から外れる」といった話を聞いたことがある方もいるでしょう。家族の扶養に入っている方が不動産を売却すると、一時的に生じる所得によって税金の負担が重くなる可能性があるため注意が必要です。
ただし、不動産を売却した方の全員が課税対象となる、家族の扶養から外れる訳ではありません。ここでは配偶者控除や社会保険の扶養の仕組み、不動産売却時にかかる税金との関係、税金対策について解説します。
今は読んでいる時間が無い!という方、この記事の要点はこちら- 扶養に入っている方が不動産を売却すると、税金の負担が重くなる可能性がある
- 配偶者控除における所得の基準は、納税者1000万円以下、配偶者133万円以下
- 不動産を売却しても、社会保険の扶養は外れない可能性がある
- 不動産売却時に税金がかかるのは、譲渡所得が生じた場合
- 譲渡所得が生じても、特例により税金がかからないケースがある
目次
1. 不動産を売却すると、配偶者控除が適用されなくなる?
配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合において、納税者の所得から一定金額を控除できる制度です。例えば、夫婦2人世帯で夫のみが収入を得ている場合、夫には所得税・住民税の納税義務が生じます。ただし、妻の収入が一定金額以下の場合は、納税者である夫の収入から配偶者控除の金額が差し引かれるため、控除が適用される分、税金の負担が軽くなります。
配偶者控除の対象となる配偶者(前述のケースでの妻)は、収入の上限が一定金額以下でなければなりません。例年の収入が一定金額以下の配偶者が不動産を売却して所得を得た場合、配偶者控除が適用されなくなる可能性があります。配偶者控除が適用されない場合、例年よりも納税者(前述のケースでの夫)の所得税・住民税の負担が増える仕組みです。
不動産の売却が所得税・住民税の納税額に与える影響を理解するためには、基本的な税金の知識が必要です。ここでは、配偶者控除の基本と不動産売却との関係について解説しましょう。
1.1. 配偶者控除は所得控除の一つ
日本では、一定金額以上の収入を得た方に対して、所得税・住民税がかかります。ただし、税金の課税対象は、収入の全額ではなく「課税所得金額」です。課税所得金額とは、収入から必要経費や各種控除を差し引いた金額です。
課税所得金額を計算する際、納税者の家族構成や個人の事情を考慮して税金の負担を軽くできる仕組みがあります。その仕組みを「所得控除」と呼びます。所得控除には複数の種類があり、その中の一つが「配偶者控除」です。
不動産売却時の所得税はいくらかかる?税金対策、検討していますか?不動産を売却すると住民税が上がる仕組みは?いつ・どうやって納税するの?
1.2. 配偶者控除・配偶者特別控除の条件とは?
正確にお伝えすると、配偶者控除には「配偶者控除」と「配偶者特別控除」という2つの種類があります。各控除で対象となる方の共通点と違いは、以下の通りです。- 納税者本人の所得が1000万円以下
- 配偶者の所得が一定金額以下
- 民法の規定による配偶者である(内縁関係はNG)
- 納税者と生計を共にしている
- 配偶者が青色事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
- 対象となる配偶者の所得の上限金額
| 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
|---|---|---|
| 納税者の所得 | 1000万円以下 | 1000万円以下 |
| 配偶者の所得 | 48万円以下 | 48万円超え133万円以下 |
配偶者控除・配偶者特別控除の基本的な考え方は、同じです。大きな違いは、控除の対象となる配偶者の所得金額の上限にあります。納税者本人の所得が1000万円以下の場合において、配偶者の所得が48万円以下であれば配偶者控除、48万円超え133万円以下であれば配偶者特別控除の対象となります。
控除額は、納税者・配偶者の所得に応じて異なるため、詳細は国税庁の公式サイトをご覧ください。
1.3. 扶養内の方が不動産を売却した場合、納税額に与える影響
配偶者の扶養に入っている方が不動産を売却すると、世帯全体の納税額が増える可能性があります。納税額が増える仕組みは以下の通りです。- 世帯主に配偶者控除が適用されなくなる
- 不動産を売却した本人(扶養に入っている方)に納税義務が生じる可能性がある
不動産売却時に得られる売買代金は、収入とみなされます。例年の収入が扶養内に収まっている方が不動産を売却して一定金額以上の所得を得た場合、世帯主に配偶者控除が適用されなくなり、世帯主の納税負担が増えてしまいます。
また、扶養に入っている方が不動産を売却した場合、売却した本人にも納税義務が生じ、世帯全体の納税額が増える可能性があるでしょう。
ただし、不動産を売却した方の全員に納税義務が生じる訳ではありません。不動産売却時にかかる税金の仕組みについては、後ほど解説します。
2. 不動産を売却しても、社会保険の扶養は外れない?
家計の主な収入を得ている方が会社員・公務員の場合、勤め先の従業員や職員を対象とする社会保険に加入しています。加入者の家族の収入が一定金額以下であれば、家族が世帯主の扶養に入っているでしょう。
「扶養に入っている人が不動産を売却すると、社会保険の扶養から外れるのでは?」
このように心配する方もいるでしょう。しかし、社会保険の場合、不動産売却時のように一時的な収入は収入とみなさないケースがほとんどです。多くの場合、社会保険の被扶養者※の収入は、継続的な収入を得ているかどうかで判断されます。
※扶養に入る方です
ただし、加入している健康保険や共済制度の運営主体によって、不動産売却時の収入に対する考え方が異なります。不安がある方は、売却前に運営主体へご確認ください。
不動産売却後に健康保険料・介護保険料が上がる人がいる? それはなぜ?3. 不動産売却で税金がかかる条件【譲渡所得の計算方法】
不動産売却時にかかる税金を譲渡所得税(所得税・住民税)と呼びます。譲渡所得税は、不動産を売却した全ての方にかかる税金ではありません。
不動産売却時に譲渡所得税が課税される方は、譲渡所得を得た方です。譲渡所得は以下の計算方法で算出します。譲渡所得=売却価格−(取得費※+譲渡費用※)
※不動産の購入金額と購入・売却にかかった費用の合計金額です
譲渡所得が生じた場合、譲渡所得に税率をかけて譲渡所得税を求めます。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
3.1. 譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なる
譲渡所得税は、所有期間が5年以下か5年超えかによって税率が異なります。所有期間が5年以下で得た所得は短期譲渡所得、5年超えで得た所得は長期譲渡所得です。
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 (所有期間5年以下) | 30% | 9% |
| 長期譲渡所得 (所有期間5年超え) | 15% | 5% |
※2037年までは上記の他に、基準所得税額×2.1%の復興特別所得税が課税されます
不動産売却時の譲渡所得について
4. マイホーム売却時の税金対策
不動産売却時に譲渡所得が生じても、特例によって税金がかからない可能性があります。マイホーム売却時の特例には、3000万円特別控除や譲渡所得の軽減税率があります。3000万円特別控除は、不動産売却時に生じた譲渡所得から最高3000万円を控除できる制度です。この特例を利用した場合、譲渡所得が3000万円以下であれば税金がかかりません。
譲渡所得の軽減税率は、所有期間10年を超えるマイホームを売却した場合、通常の譲渡所得税の税率よりも低い税率が適用される制度です。3000万円特別控除と軽減税率は併用できるため、譲渡所得税の負担を大きく軽減できるでしょう。
また、特例の他にもふるさと納税を利用してお得に節税できる方法があります。
マイホーム売却時の特例やふるさと納税を利用した税金対策については、以下の記事をご覧ください。
【3000万円の特別控除とは】不動産売却で必要な税金の知識所有期間が10年を超えるマイホーム売却時の特例|ポイントをわかりやすく解説
不動産売却時にふるさと納税で節税する仕組み・計算方法・注意点
5. 不動産売却後は確定申告を忘れずに!
譲渡所得税が生じた場合や特例を利用する場合は、確定申告が必要です。確定申告の時期は、不動産を売却した年の翌年2月16日から3月15日までとなります。不動産売却後は忘れずに手続きをしましょう。
不動産売却後の確定申告と注意点6. まとめ
扶養に入っている方が不動産を売却した場合、一時的に世帯の納税額が増えることがあります。ただし、譲渡所得税は全ての方に課税される税金ではありません。マイホーム売却時は特例制度も設けられているため、高額な税金がかかるケースは多くないでしょう。
とはいえ、高額な資産である不動産の譲渡所得税は、税額が高くなる傾向にあります。不動産の売却を検討している方は、制度を上手に利用して税金対策をしましょう。
- 扶養に入っている方が不動産を売却すると、税金の負担が重くなる可能性がある
- 配偶者控除における所得の基準は、納税者1000万円以下、配偶者133万円以下
- 不動産を売却しても、社会保険の扶養は外れない可能性がある
- 不動産売却時に税金がかかるのは、譲渡所得が生じた場合
- 譲渡所得が生じても、特例により税金がかからないケースがある
この記事のポイント Q&A
配偶者控除とは?
納税者に配偶者がいる場合において、納税者の所得から一定金額を控除できる制度です
詳しくは<1.不動産を売却すると、配偶者控除が適用されなくなる?>をご参照ください。
マイホーム売却時の税金対策とは?
不動産売却時に譲渡所得が生じても、特例によって税金がかからない可能性があります。
マイホーム売却時の特例には、3000万円特別控除や譲渡所得の軽減税率があります。3000万円特別控除は、不動産売却時に生じた譲渡所得から最高3000万円を控除できる制度です。この特例を利用した場合、譲渡所得が3000万円以下であれば税金がかかりません。
詳しくは<4.マイホーム売却時の税金対策>をご参照ください。
関連特集記事
-
不動産売却にかかる税金と損しないための節税方法
課税譲渡所得の計算方法から、特別控除の詳しい説明、提出が必要な資料について解説
【記事作成日】 -
不動産売却時にかかる消費税
不動産売却における消費税の扱いから計算方法まで
【記事作成日】 -
不動産売却後の確定申告と注意点
煩雑な確定申告と必要書類から注意点まで解説
【記事作成日】 -
不動産売却時の税金計算方法とシミュレーション
不動産売却時の税金計算方法から譲渡所得税シミュレーションまで
【記事作成日】 -
【3000万円の特別控除とは】不動産売却で必要な税金の知識
3000万円の特別控除の詳細からその他の特例制度まで
【記事作成日】 -
不動産売却時の譲渡所得について
譲渡所得税の仕組みからシミュレーションまで
【記事作成日】 -
不動産売却時:取得費の計算方法とは
譲渡所得を計算する際の取得費の計算に必要な知識からシミュレーションまで
【記事作成日】 -
不動産売却で贈与税がかかる場合とは
贈与税の基礎知識から負担を軽減させる方法まで
【記事作成日】 -
不動産を売却した場合の固定資産税について
買主との清算方法から確定申告時の注意点まで
【記事作成日】 -
不動産売却時の節税対策
個人・法人が不動産を売却する際にかかる税金の種類から特例制度まで
【記事作成日】 -
不動産売却にかかる印紙税とは
印紙税に関連するQ&Aから節税できるケースまで
【記事作成日】 -
不動産売却時にふるさと納税で節税する仕組み・計算方法・注意点
節税できる仕組みやふるさと納税の控除上限額の計算方法、制度利用時の注意点
【記事作成日】 -
不動産売却時の所得税はいくらかかる?税金対策、検討していますか?
不動産売却時にかかる譲渡所得税(所得税・住民税)の仕組みや計算方法から税金対策まで
【記事作成日】 -
不動産を売却すると住民税が上がる仕組みは?いつ・どうやって納税するの?
不動産を売却して住民税が上がる仕組みや納税方法から税金対策まで
【記事作成日】 -
所有期間が10年を超えるマイホーム売却時の特例|ポイントをわかりやすく解説
所有期間が10年を超えるマイホームを売却した際に適用される特例のポイント、確定申告について
【記事作成日】 -
分離課税とは?不動産売却後にかかる税金の仕組みとシミュレーション
不動産売却後にかかる税金の計算方法や税額に影響する3つの要素、利用できる特例制度など
【記事作成日】

あなたの不動産を無料で査定